[時評1:あとがき/photographers' gallery 2003.8.4:http://www.pg-web.net/]
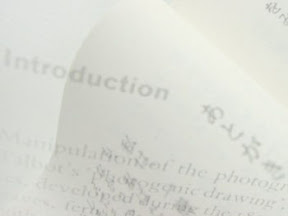
いつ頃からの習慣なのかは知らないが、本にはあとがきというものがついていることが多い。文庫だと、あとがき・文庫版あとがき・解説…と、2、3の文章が巻末に添えられていることもある。手もとにある本を適当に見ただけなので確かなことは言えないが、翻訳書や洋書では、序やintroductionが巻頭にあるものがほとんどなので、あとがきというのは日本的な習慣なのかも知れない。
実際には序のようなあとがきも、その逆もあるし、自著に言及するという意味では、あとがきも序も同じようなものだとも言えるだろうが、ある種の自注がはじめにあるか終わりにあるかというのは、やはりその内容にも影響するだろう。序にあとがきのような締めくくりを書く人はいないだろうから。
自注を書く行為というのは、読者でありかつ著者であるような二重性を持っている。あとがきには、その二重性が最後になって明かされるようなウェットな感触がある。例えば、複雑なテクスト論を展開した批評のあとがきで、この本は自由に読んで欲しいといったことが書かれていたりすると、大人になってゆとりの時間を強制されたような、真面目な議論の後に「なんちゃって」*1と言われたような、何とも奇妙な気分になってくる。
そんな気分を最も強く感じたのは、かつて、書くことは生きること、というようなことが書かれたあとがきを読んだ時だった。批評と思って読んできたものが、人生だったのかと思うと苦々しく、すぐに本を処分してしまったので、正確にそういうふうに書いてあったかどうかは定かでないのだが、当時はその部分がよく引用されていたりもしたので、記憶に残っている人もいるだろう。
こうした例に限らず、いわゆる批評や評論には、ウェットな二重性を孕んだあとがきが多い印象がある。言語の二重性には敏感であっても、あるいは敏感であればこそ、それを記述することの透明性には盲目的にならざるをえないということだろうか。そうした透明性への信頼の生々しさに加えて、当時のわたくしは、契約書は契約の一部であるように、書くことは生きることであるというよりも、生きることは書くことだと考えていたので、耐えがたい違和感を覚えたのだった。
*1「なんちゃって」という言葉を使って、“transcendental nanchattebility”という画期的な(!)概念を展開した文章を思い出し、ひさびさに読み返してみたところ、偶然なのかその本にはあとがきはなかった。